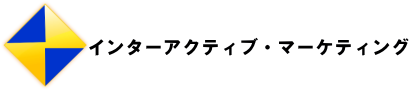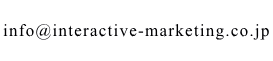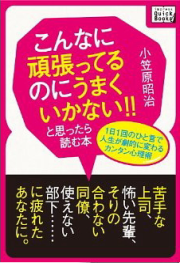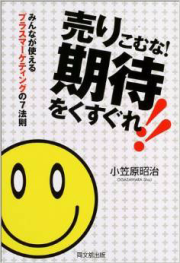社名と社章(ロゴマークとロゴタイプ)に込められた意味

社名のインターアクティブを直訳すると、相互作用性。
買う人がいて、売る人がいる商売(ビジネス)は、まさに相互作用の取引。
その、商売の仕組みを体系化したのがマーケティング。
マーケティングは「買ってよかった」「売ってよかった」と双方が満足できる取引を実現すること。
その相互作用性を、矢印の組み合せで風車のイメージに図案化し社章に(風車の理論)
黄色は陽気で明るい希望を、青は沈着冷静な戦略を表現(ゲーテの色彩論)
ロゴタイプは、行動指針の「自然体流」を表現すべく、流れるような書体に。
ゲーテの色彩論
光に一番近い色が黄色で、闇に一番近い色が青色であるとする、黄と青を両極とする色彩論。
色は、黄と青を両端にして、赤を頂点とする三角形に配置され、黄と青は呼び求めあい、黄が橙を、青が紫を経て合一し、第三の色である赤を生成(色の三原色)
風車の理論
新日本プロレスの黄金期にアナウンサーを務めた古館伊知郎氏が名づけたアントニオ猪木のプロレス哲学。相手の力を風になぞらえ、風力が強かろうと弱かろうとその風力を抗わず、自然な形で取り入れることで、自分のみならず相手をも輝かせつつ勝利するという理論。
[ミニ知識]代表・小笠原のブログでは社章の色を反転させています